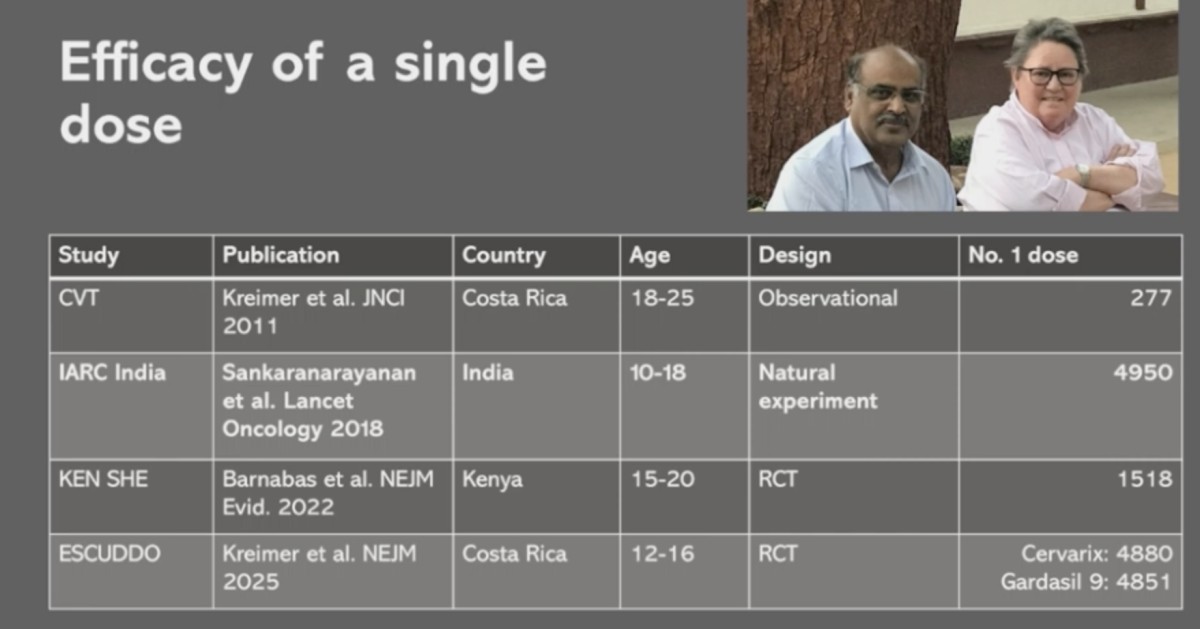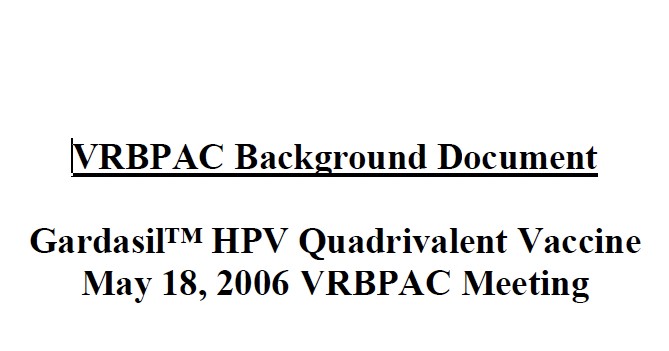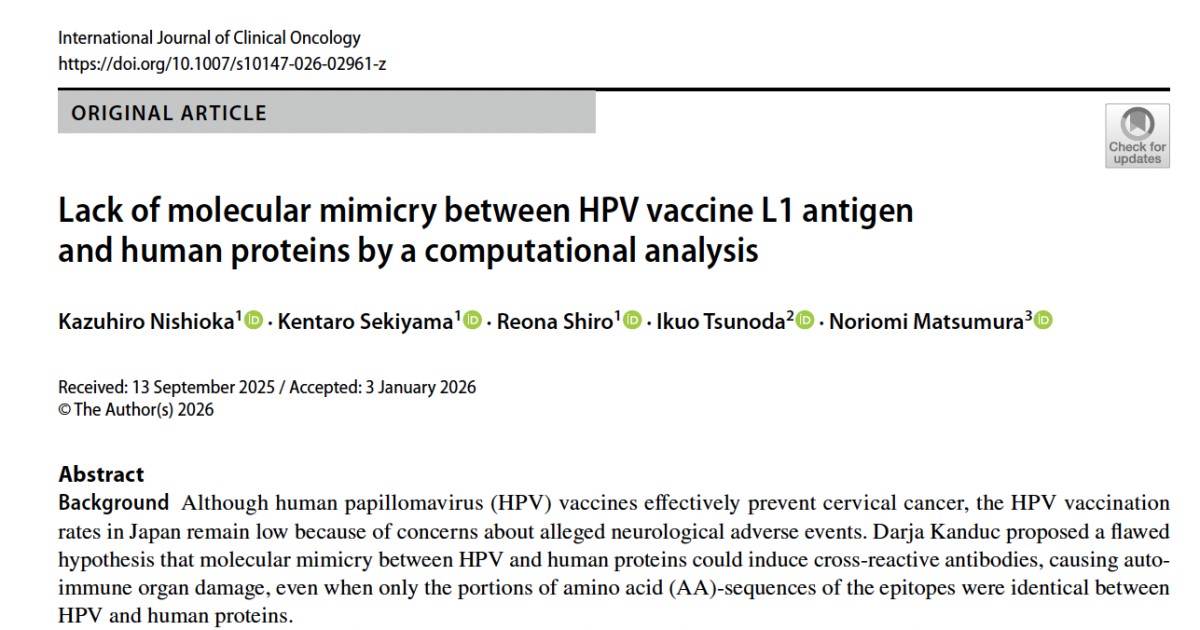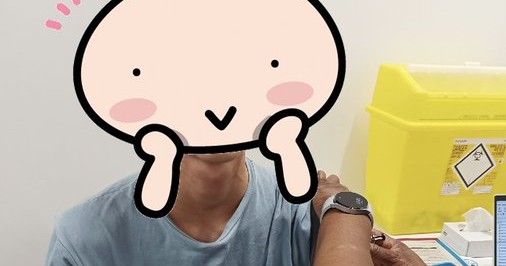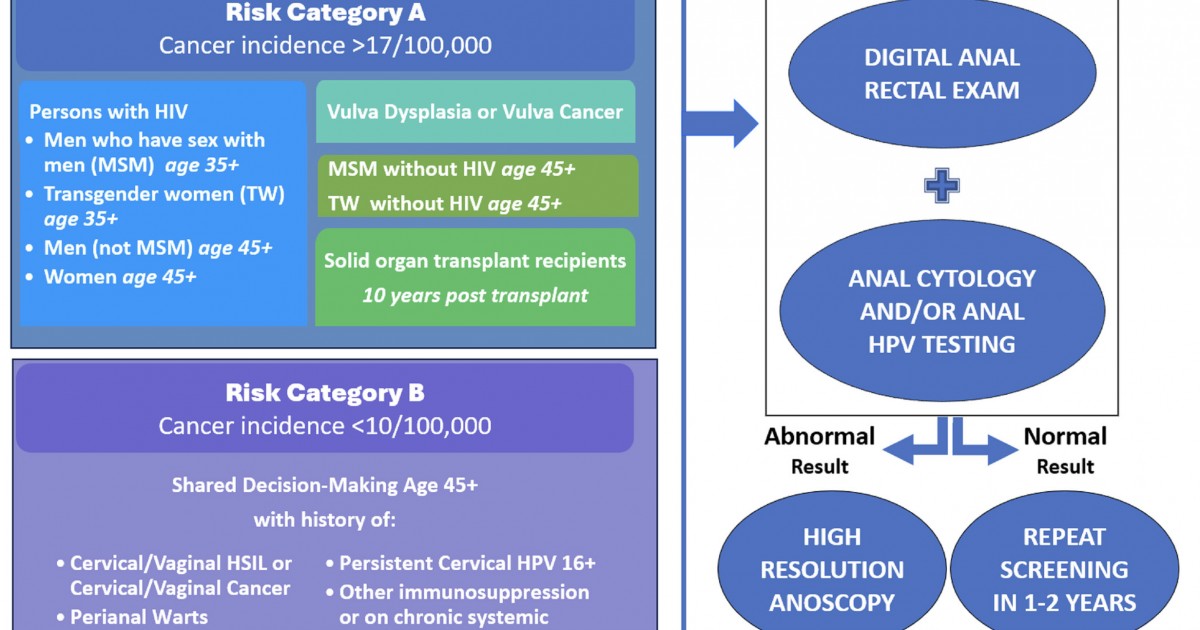HPVの存在証明⑤免疫学の登場(B型肝炎ウイルスの存在証明)
『微生物と病気の因果関係』をコッホの原則に基づいて検討していく過程で
①濾過滅菌できない(非常に小さい)感染性病原体として
②純粋培養で増殖・ふやすことのできない病原体として
ウイルスという概念が確立されていった(前回までの話はこちら)。
③感受性のある実験動物がいない場合、動物実験で感染性・病原性が確認することはそもそも不可能だ。
感受性をもつ動物がいないこと・感染しても病気として発症するのが極一部であること・感染から病気としての発症までの期間が実験で示すことのできる範囲を超えていることが、病気とウイルスの因果関係を示すことのハードルとなった。コッホの原則に示された方法とは違ったやり方で『そのウイルスがその病気の原因でないのではないか・他に原因があるのではないかという反証』を抑えて、そのウイルスと病気の因果関係があるということの妥当性を示す必要がある。今回は、本格的に分子生物学が登場する以前・ウイルスの本体であるウイルスゲノム(核酸そのもの)の配列を扱うことができる以前の話になる。人痘や動物・植物(タバコモザイクウイルスとかそう)をホストとするウイルス性疾患など、濾過性病原体として(見えないけど)感染性・病原性が確認されているものは既に実験的に『ウイルスとしての存在』と病原性がわかっていた。それらのウイルスとはまた一つ違った方法がいる。
抗体とそれに対応する抗原の発見
副題を免疫学の登場としたが、ウイルスの病原性に関する部分だけに絞って話をする。それだけでシリーズが成立してしまうから。
ある病気(感染症)に罹った人が2度と同じ病気に罹らないこと(免疫)は経験的に知られていて、天然痘に対して人痘法による免疫成立を狙った試みは古くから行われてきた(ワクチンの先駆け)。人痘は天然痘そのものであるから、接種した場合の重症化リスクが高い。自然感染よりリスクが低いとすれば、接種時のウイルスの量(感染する細胞数)が自然感染より少ない・制御できることによる感染から・病原性の発揮・免疫応答の誘導のダイナミクスが感染制御の点から有利なことになるだろうか?
これは、同じ感染性病原体に感染すると言ってもその程度に多寡があり、その後の病原性・転機に大きく影響を与えるということだ。コロナウイルスに感染するにしても、感染時のウイルス量を減らすことは大きな意味があるのと同じね🐰
ジェンナーの種痘法(最初の本格的なワクチン)の開発は、天然痘に対する交差免疫は成立するが、病原性の異なる(弱い)天然痘の近縁ウイルスを発見しワクチンとして利用できるようにしたということになる。これを実験室の中で故意に行えば『弱毒化』ワクチンの開発ということ🐰
ワクチンによって獲得免疫は①液性免疫と②細胞性免疫の二つに大きく分けられる。細胞の外にある病原体に対して働くものが液性免疫で、細胞内の病原体に働くのが細胞性免疫だ。対象とする病原体のいる場所が異なるので、その作用機序は全く異なるし、標的とする病原体側の抗原も異なる。
ウイルス粒子表面抗原を免疫原とするCOVIDワクチンとHPVワクチン。COVIDワクチンの誘導するS抗原に対する液性免疫・細胞性免疫は、ワクチンによる感染防御能・病原性抑制能発揮時に大きな役割を果たす。一方HPVワクチンの誘導する液性免疫・細胞性免疫。液性免疫は感染防御能に大きな役割があるが、細胞性免疫は全く働かない。どちらもウイルス粒子の表面抗原を免疫原にしているというのに🐰
細胞性免疫を評価するのは今でも簡単なことではない。細胞内に寄生する病原体に対する『免疫細胞のレスポンス』を定量しなければいけないから。一方、液性免疫を評価・定量する方が比較的簡単。理由は液性免疫が、(細胞全体のレスポンスではなく)抗体という分子がになっているために、抗体という分子を取り出して評価することが可能だからだ。
液性免疫は北里柴三郎に始まる
これも深入りはすまい🐰
北里柴三郎の業績は、『破傷風菌純粋培養』成功した・病原体と病気の因果関係を証明する上での『病原体の同定』(定義)することに成功した・続いて、破傷風菌が感染することによって起こる病気・病原性を抑制する液性因子『抗毒素』を発見し、その『抗毒素』を誘導し治療に使う方法『血清療法』を開発したことだ。
コンボが凄すぎてもうね🐰
破傷風菌感染による病原性の発揮・破傷風を担う因子として『破傷風トキソイド』が同定され、トキソイドをワクチンとして用いて、あらかじめ抗毒素を体内に産生させるのが、破傷風ワクチンになる。この『抗毒素』が現在抗体よばれ、液性免疫を担う主体だ。抗体とは特定の分子に特異的に結合し、結果免疫応答を誘導できるものということができる。この抗体の同定・定量・評価を通じて発展したのが免疫学のうちの液性免疫の分野ね。
体内に異物(もともと体に存在しない病原体由来)に対し『特異的に結合することのできる抗体』が誘導(濃度が高くなる)される。これが液性獲得免疫。感染する前には存在しなかった(濃度低かった)抗体が、感染(ワクチンの投与)後に誘導される(濃度が高くなる)。
この『ある(病原体由来の)抗原と特異的に結合できる抗体の出現』を用いてある病原体の存在を同定するのが、血清学的な(同定・検出)法だ
コッホの第一原則を置き換えるものがこれ(重要)🐰 特定の病気において特定の細菌が観察される(コッホの第一原則)が、特定の病気において特定の抗原や抗体を検出することによって観察することによって置き換えられるってわけ。
・そのような抗原と抗体が存在すること。
・病態の有無・病気にかかっているいないで、そのような抗原・抗体の存在・量がかわること。
この二つで、目に見えないウイルスという存在を確認する🐰
技術的には、抗原や抗体の検出・定量法の開発ということになり『免疫沈降法』や『寒冷凝集』、『免疫染色』や『ELISA』、COVIDで言えば抗原診断キットはCOVID由来の特異的な抗原とそれに対する特異的な抗体を用いることで検出する。
さあ、目に見えないウイルスを検出方法を手に入れたというわけだ🐰いってみよう
複数の病原体が同じ病態の原因になること・感染して病気が発症しないことがあること
コッホが示した感染性病原体と病気を証明する方法『コッホの原則』において、病原体の存在と病態が同時に存在することは非常に重要なポイントであった。ある病態(結核と臨床的に定義できるもの)において特定の病原体(結核菌)は常に存在しなければならなかったし、病態が存在しなければ(健康な人において)病原体は存在してはいけなかった。病態と病原体の対応は一対一で強固なものであることが要求される。
これが細菌感染症においてもあてはまらないことは『腸チフスのメアリー』を例にあげることができる。ウイルス感染症においては非常に一般的であることがわかってくる。
フリーでアクセスできる論文としてはこれがいいかな🐰
これは、ウィスコンシン大学の学生で臨床的に呼吸器感染症と診断された人のサンプルをもちいて、血清学的検査法を用いて、どのような特異的な抗原・病原体(ここではウイルスを想定)が存在するかを抗体を検出することによって同定したものだ。
・今まで知られている(既知)の病原体に対する抗体が検出されなかったものが半分
つまり、病気の原因がわからない。原因不明の呼吸器感染症であった一方、
・アデノウイルス・インフルエンザ・パラインフルエンザ・オウム病・ヒストプラズマ・イートンウイルスなど、さまざまな病原体に対する抗体価の上昇が見られたものが半分
であった。
臨床上鑑別が可能かの問題はあるが、ある程度似たような病態として、異なる感染性病原体が同じ病態の原因になりうるということは『コッホの原則』に反するものとなる。また、この時点では病態に関連した抗原の出現に対する反応として特異的な抗体の上昇として検出しているために、その病原体はウイルスに限定されない。
オウム病はクラミジア・ヒストプラズマは真菌・イートンウイルスはマイコプラズマであった。分離培養が困難であるか、細胞内寄生性で無細胞系での培養法がないもの、ウイルスではないが小さいために濾過性病原体として同定されたもの、それぞれコッホの原則上は一筋縄で行かない病原体たちであったが、血清学的手法でその存在は検出・証明されるということ🐰
風邪様症状を主体とする感染症・皮疹を主体とする感染症群(麻疹や風疹・突発診)など、鑑別可能(臨床上病態が異なる)であるものがある一方、症状としてはオーバーラップしている部分も大きい。
また、病原体の抗原やそれに対する抗体の検出ができるようになったことは、病態の存在しない・ざっくり健康といえる人たちの中にその病原体が存在すること『無症候性の感染者』『持続感染』が存在することがわかるようになった。これもコッホの原則上は大問題だ。病気でない人の中から病原体が見つかれば、病態と病原体の関係性が弱いものとなる。発症のためにはホスト側の因子が重要となり『ホスト』と『細菌・寄生虫・ウイルス』相互関係として感染症学の重要なテーマとされるものになる。
B型肝炎とB型肝炎ウイルス
じゃあB型肝炎ウイルス感染とB型肝炎の間の因果関係が証明されていく過程を例に見ていこう🐰(この分野にはより詳しい人が多いだろう。訂正があると勉強になる)
①血液中の蛋白質の構成を調査するというプロジェクトの中で、血友病のために輸血を頻回に受けた人に含まれる抗体が、オーストラリアのアボリジニからの血清サンプルと反応することが発見された。
輸血を頻回に受けた人はさまざまな異なる抗原に晒されることが多く、それだけ多くの抗体が誘導されていると考えられた。血清中の抗体のポリモルフィズム(多型性)調べるのには適したサンプルと考えられたのは妥当だろう。地理的にも全く離れた2人の間に、特定の抗原(蛋白質)とそれに特異的に反応する抗体が存在することが発見された。
抗体の存在を介して”何かの抗原”があることがわかった(発見された患者の出身地からオーストラリア抗原"Au(1)"と名付けられた)。
②この血友病患者のサンプル(Au(1)に対する抗体を含む)を用いてスクリーニングをかけたところ、Au(1)を持つ人の割合に偏りがあることがわかった。
健康なボランティアに比較して白血病の患者が100倍この抗原Au(1)を持つ確率が高い。現在となっては白血病の治療の過程で輸血を頻回にうけることが、(当時は無防備であった)B型肝炎ウイルスの感染リスクが高くなった結果と解釈できる。当初は白血病の発症に関する抗原の可能性として考察されたのは妥当だろう。
③Au(1)と白血病の関係を調べるために、ダウン症の患者を対象にAu(1)のスクリーニングを行う過程で肝炎との関連が指摘された
ダウン症は白血病の発症リスクが高いために適した研究対象と考えられた。その中で、Au(1)の出現率が確かに、他の通常の集団よりも高いことがわかった。しかも、年齢が高くなるほど陽性率があがる。これは『抗体が認識する抗原の量に変化があった』ことで説明できる。当然感染性因子の存在が頭に浮かぶ🐰
そして、ついに一つの症例に出会う。時間をおいて複数回サンプリングが行われた患者において、前回までは陰性だったのに、ある時陽性化したわけ。この期間の間にAu(1)がその人の中に出現したということになる。そして、その間に肝炎が発症していた。
肝炎が感染性の因子で起こるであろうことは、ざっくりとわかっていた(輸血後に肝炎が起こりやすいことなど)。ここで、仮説が成立する。『オーストラリア抗原"Au(1)"に関係する感染性因子と肝炎の間に因果関係がある』→『オーストラリア抗原"Au(1)"と関係するウイルス性の肝炎が存在する』ということ。
さて、問題は多くのウイルスと同じようにB型肝炎ウイルスには(当時)培養系も動物実験系も存在しなかった。特異的な抗原と抗体の存在を軸に病原性を示す試みが始まった。
無数の科学者の執念と忍耐強さよ
さあ仮説がたったので研究もしやすくなった。『オーストラリア抗原"Au(1)"関連するウイルスによって肝炎が生じる』。これを証明すればいい、証明とは妥当な疑いの範囲を超えて正しいといえるエビデンスと解釈を提出し、反証がでるまでのあいだ正しいと言えれば良い。道具は二つ『特定の抗原と抗体』になる。コッホの原則はどこかに行った(純粋培養できないのだから当たり前だ)?
①健康な一般集団ではAu(1)の出現率は0.1%なのに、肝炎を発症した人では出現率が高い。輸血や静注を受けたことがある場合は実に60%以上、そうでない場合も30%の例において、Au(1)が血清中に検出される。
これが、コッホの第一原則と同じであることがわかるだろうか。ある病気の人のサンプルから特定の病原体が観察される代わりに、肝炎の患者中のサンプルに特定の抗原が観察されるわけだ(目に見えないものを理解できない人はおいておこう)。
そのほかの肝臓に影響を与える疾患においてAu(1)の検出は見られなかった。肝炎に特異的な抗原ということができる。
②Au(1)は急性肝炎だけではなく、慢性肝炎においても出現した。
明らかな感染エピソード(輸血など)がある場合にAU(1)の出現が誘導されることが(数日〜数ヶ月)わかるとともに、世界中(日本も含む)研究者らによって、慢性持続性肝炎の患者の血清の中にAu(1)が高い確率で存在する。普遍的な現象として捉えられた。
③抗体を用いてAU(1)の精製が試みられ、その物理・化学的性状が明らかになった。Au(1)は粒子の構成要素だ。
そのほかの血清成分と違う性質があることが示され、抗体に反応することを指標に分離・精製を試みる過程でAU(1)を含む粒子の密度が測定された。加えて、電子顕微鏡でその精製サンプルに直径200Aの粒子用構造があることがわかった。抗体を用いるとその粒子が凝集することから、Au(1)がその観察された粒子に存在することが示唆された。
その精製されたAu(1)を含む粒子には核酸(DNAやRNA)は含まれていなかった。不完全なウイルス粒子(精製の過程で破壊されてしまった)ウイルス粒子と考えられる。(原著ではソーセージ様とかドーナッツ様とか表現が面白い)🐰
④AU(1)に対する抗体がウサギ・マウスなどで作製され、肝炎を起こしている肝臓にAu(1)が存在することがわかった。
AU(1)を含む血清をウサギ・マウスに接種して抗体を誘導、AU(1)を含まない血清成分に吸着される抗体を除いてやれば、AU(1)に対する抗体が作製できる。抗体が精製できれば蛍光物質で標識することによって、蛍光抗体法によって観察ができるようになる。
この抗体を用いて血清中AU(1)が存在し(肝炎を発症している)患者の肝臓組織にAU(1)が存在することがわかった。対照の肝臓にはAU(1)は存在しない(コッホの…略)🐰
⑤AU(1)が検出される血液・検出されない血液、輸血をすると前者で肝炎が発症する。
ドキッとする研究と言える。この時点までで、AU(1)を含む粒子と関連するなにか(ウイルスなんですけどね)が人から人、おそらく輸血などを通じて感染・肝炎を発症させていると推定するある程度の証拠が存在したと言える。
そこで、輸血用の血液を輸血をAU(1)の有無でわけ、輸血を受けた患者で追跡すると、AU(1)陽性の血液を輸血された患者で肝炎が発症する。加えて、肝炎を起こした患者でAU(1)に対する抗体が誘導されることがわかった。
これは強力なエビデンスで、この時点までに感染性(ウイルス性)の肝炎がAU(1)陽性の血液では起こる。AU(1)陽性の血液にはその様な感染性因子があることはほぼ確実となった。
AU(1)を含む粒子に感染性と病原性があることが一定のエビデンスで示されたわけだ。
もちろんこの様な実験・観察は『AU(1)を含む粒子に感染性と病原性があることが一定のエビデンスで示される』前でないとやってはいけない。結果的にはコッホの原則で言う『感染性・病原性』の確認がなされたとも言える。
⑥AU(1)が検出される血清を血中に投与すると肝炎が発症し、AU(1)とそれに対する抗体が誘導される。
これは倫理的な視点から見た場合(少なくとも今日には)許されない実験だったと言える。専用の施設にある障がいのある子どもたちを対象(その様な施設でウイルス性肝炎のクラスターが発生していたのが背景にある)に、肝炎を起こすと考えられていた感染性病原体(ウイルス)を含むサンプルを投与実験をした。簡単なまとめはここにある、孫引きもできる。
ここでは、2種類のウイルス性肝炎(現在のA型肝炎とB型肝炎)があることと、免疫グロブリン療法の効果が確認された。ヒトを使っての感染性・病原性の確認が行われたわけだ。
また、投与されたAU(1)の量と比較して、患者の中で産生されるAU(1)の量は圧倒的におおくなることが確認された。これはAU(1)を含む肝炎誘導因子が毒物などの物質ではなくヒトの体内で増殖・増幅されるものであることをしめす。
⑦AU(1)が検出される肝炎が『感染症』であることの疫学的なデータ
⑧感受性のある動物が存在し、感染実験が行われた。
AU(1)を含む感染性病原体はヒトとヒト以外の霊長類に感染性を示し、そのほかの動物には感染性を示さなかった。これは、ポリオウイルスがヒトとヒト以外の霊長類にのみ感染する時の理由と同様に、AU(1)を含む感染性病原体が胆汁酸取り込み輸送体NTCP/SLC10A1を受容体に細胞に感染するからであった。NTCP/SLC10A1が発現する動物のみAU(1)を含む感染性病原体は感染できる。
肝臓の細胞にしか感染しないこともこれによって説明できる🐰

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4246769/ 今回のレターはこの総説の一部への注釈🐰
『これまでデータを総合すると、AU(1)を含む肝炎誘導因子はウイルスだ』そして『証明されたとは言えないが、これまで集められたエビデンスはそのことをサポートする』。もし、ウイルスでないとしたら、AU(1)とは異なる未知の(だがAU(1)と強い関係のある)生物学的な何かだろう。だがそうだとしても興味深い🐰
証明されていないとは、もちろんコッホの原則に示された完璧性が念頭にある『AU(1)とは異なる未知の(だがAU(1)と強い関係のある)生物学的な何か』がこの肝炎原因になっている感染性病原体の本体かもしれないといえるわけ。
で次が重要だ。実質的に『科学者たちは』・AU(1)を含む肝炎誘導因子はウイルスで肝炎の原因となっている病原性因子であることで合意した。反証がでるまでは正しいこととして有効だ。
証明が不十分だとしても『AU(1)を構成因子とするウイルスが肝炎の原因となっていること』この理解をベースに、いろいろな臨床上の問題に対処することができるようになる。
例えば、
・感染対策ができる様になった。
血液を介して感染することがわかった。注射針の使い回しが危険である根拠がひとつ確立した。輸血を介して感染していることがわかったため、輸血様の血液をAU(1)の存在の有無でスクリーニングをかけると、危険な血液とそうでないものを分けることができる様になった。
職業的売血を行うヒトでAU(1)の陽性率が高いことがわかり『売血』をやめることに対する正当性を提供した。
臨床の現場で血液を介した感染のリスク評価・管理の必要性の根拠となった。
・診断法が確立した
HBs抗原がAU(1)だよ🐰そしてこのウイルスはB型肝炎ウイルスだ。
・ワクチン開発の道筋ができた
AU(1)”HBs抗原”ウイルス粒子の表面蛋白質。それを免疫原としてB型肝炎ワクチンが開発された。当初はB型肝炎罹患者の血液から非感染性のHBs抗原を精製してくると言う力技であったが、分子生物学の進展とともに”みんな大好き”遺伝子組換え技術を用いて、酵母でHBs抗原を大量生産できる様になったことからワクチンの開発が成功した。
証明が不十分(実際は誰もその様には考えていない、科学はAbsolute Truthを扱わないと同じ様な意味だ)だとしてもなにが問題だろうか?B型肝炎ウイルスはこの様に同定・定義され、その存在と感染性・病原性がエビデンスによって支持されている。
そして、この知見に基づいたさまざまな対策は、感染予防・診断法・効果的で安全なワクチンの開発へと結実した。厚労省がウイルスの存在を証明する文書を持とうが持っていまいが関係ない、実用性の部分で十分な結果を出している。
AU(1)”HBs抗原”が検出される血液をワクチン未接種で輸血されてもええんか?
まとめ
B型肝炎ウイルスとB型肝炎の因果関係を証明する過程を通して、免疫学(血清学)を利用した病原体の同定・存在の検出と病気との因果関係を示すエビデンス・証明を追体験した🐰
あれ?血清学的評価としてもう一つHPVと違うウイルスを扱う予定だったが、長くなりすぎた。次にする。次回は”病態の存在しない・ざっくり健康といえる人たちの中にその病原体が存在すること『無症候性の感染者』『持続感染』が存在すること”、その様なウイルス感染症の病原性をどの様にみてきたかになる予定。
B型肝炎ウイルスを発見したブランバーグは1976年のノーベル賞を与えられた。
すでに登録済みの方は こちら